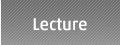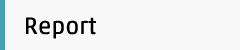ニューヨークにおける2つの非営利芸術団体「パブリックアート・ファンド」、「ジャパン・ソサイエティ」の報告。
2003年も大詰めの忙しい時期に、無理を言って写真家デニス・コールウッドと陶芸家ケイコ・フカザワ夫妻の自宅を訪ねた。お手製のグラフィティシャツを身にまとった2人に案内され家の中に入ると、何ものかわからない力に圧倒された。リビングやダイニングのあちらこちらに彼らの作品が並べられている。壁には写真とグラフィティのコラージュ、床には青や白、黄色を基調とした大皿や壷がある。鑑賞するうちに、そのひとつひとつがコラボラティブ・ワークであり、その作品に関わった一人一人の存在感が全面に溢れ出ていることに気付いた。これだ!と思った。こんなにも力強いアートワークに出会うのは久しぶりな気がする。そしてそれらは、いわゆる道を外してしまった若者たちとデニス、ケイコとのアーティスト対アーティストとしての真剣勝負なのだ。

彼らとのコラボーレーションのきっかけは偶然だった。社会問題と向き合う写真を撮り続ける傍ら、ロサンゼルスの少年更正院にて20年以上保護観察官を務めてきたデニスがギャングメンバーたちのタトゥーに好奇心をそそられ、彼らのモノクロ写真を撮り始めた。しかし、その写真の膨大な数にモデルが誰なのか判別することが困難になった写真家は、少年たちに自分が移っている写真にサインするように頼んだ。すると、一人の少年がその写真の上にギャングの象徴であるグラフィティを描き始めたのだ。

時を同じくして、ケイコも女性専用刑務所で美術教室のインストラクターとして働いていた。そこで、彼女は大きな白焼の壷を割り、そのひとつひとつの破片を使い、生徒たちそれぞれの母への記憶や思いを描いてもらった。それをまた元の形に戻し、その後手を加えて自らがひとつの作品として完成させるというプロジェクトを行っていた。壷を割り、破片に手を加え、元に戻すというアートメイキングが罪を犯してしまった過去を打ち破り、新しいものに生まれ変わるというコンセプトを意味しているとケイコは語ってくれた。

そんな2人が出会い、結婚して5年になる。期せずして発見したギャングスターたちの芸術的才能と自らのモノクロ写真と彼らのグラフィティとの融合。その頃、少年更正院にアートのプログラムも設立された。デニスはそのひとつのクラスを担当することになり、それ以来、『ギャングアーティストたち』とのコラボーレションは彼のライフワークとなる。ケイコもすぐにデニスのプロジェクトに共感し、自らもその少年たちとセラミックを表現手段としコラボラティブワークを始める。人々が目を細めるようなギャングのグラフィティの中にデニスとケイコは美を見出したのだ。少年たちの素顔と言ってもいいだろう。塀の外では、社会や敵対するギャングチームに対する挑発的なメッセージであり、時にはそれを描くため命を落とすものさえいるグラフィティも、デニスのクラスでは純粋に自分を表現することができるアートだった。そして、彼らは何かを破壊するのではなく、何かを創造する楽しさ、達成感を学んだ。デニス自身、少年更正院のことを “a safe place” と表現する。「僕はただ彼らのいいところに光を当てたかったんだ。それがアートであったのはとても自然なことだよ。」
彼らの作品がいくつかのギャラリーに展示されるようになった。好意的な反響が多い中、否定的な意見こともあった。「デ二スとケイコはギャングを奨励している」「ギャングを正当化している」との声だった。しかし、ふたりはグラフィティこそアメリカの現代文化・サブカルチャーを象徴する新しいアートの形だと主張する。デニスは少年たちの才能を最大限に引き出そうと、クラスの中で彼らが描くものをいっさい制限しなかった。時には性的な内容を描くものもいたが、ケイコは浮世絵風な官能図をそのとなりに並べそれに応えた。しかし、ほとんどの少年はガールフレンドや家族など外の世界に残してきたものや自分の過去に対する複雑な感情が作品に表れた。苦悩、後悔、切望、夢。これまでの人生を自叙伝的にデ二スの写真の上に綴った者もいる。敵対するチームのギャングメンバーたちさえ席を並べて制作活動に没頭するうちに同じアーティストしてのライバルとなった。当初は院内の壁に『らくがき』していたギャングスターたちもデ二スのクラスを続けたいが故に『課外活動』は控えるようになった。施設を破壊する行為とみなされ、クラスからキックアウトされてしまうからだ。最終的に驚くほど壁のグラフィティはなくなったという。

アートは自らを表現する手段であると同時に生きる糧にもなる。絵空事といわれてしまうかもしれないが、デ二スやケイコのような大人が世の中にもっとたくさんいたら、ギャングスターになる少年たちは減少するのではないだろうか。道に迷わず、いや、たとえ迷ってもやさしく導いてくれる彼らがいるから、子供たちは何度でもやり直すことができるのではないだろうか。ふたりは少年たちを一人の人間として認め、一人のアーティストとして尊重しているのだ。人と人との単純で純粋なコミュニケーションから生まれ、飾ることなく自分を表現した作品だからこそデニスとケイコのアートはパワフルなのだ。最後にデニスは「My kids made this for me」とショルダーバッグを見せてくれた。白いキャンバス地のバッグ一面にグラフィティが描かれていた。塀の中の少年たちを『My kids』と呼ぶデ二スを同じ大人として、アートに従事する者として誇らしく思った。
Junko Sudo