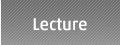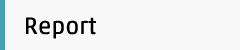6月末、筆者は、芸術文化マネジメント関連の国際学会に参加するため南米コロンビアの首都、ボゴタを訪れた。コロンビアというと、麻薬マフィアや反政府ゲリラが暗躍する危険な国という印象があるかもしれない。確かにボゴタの街には、犬を連れた警官や機関銃を持った兵士、民間の警備員などが数多くいて、常に警戒態勢という感じだが、ウリベ前大統領(2002~2010在任)が治安対策に重点的に取り組んだ結果,殺人や誘拐の件数は大きく減少しているという。740万の人口を擁するラテンアメリカで6番目の大都市ボゴタ。その中心部には、活気に溢れたストリート文化があった。

①日曜日の歩行者天国。フードから雑貨、アクセサリー、本、携帯電話まで、あらゆるものが露店で売られている

②幹線道路沿いのコンクリート壁には、たいていこのようなグラフィティが描かれている
(Crisp)の名で壁画制作をしているオーストラリア人のアーティスト、クリスチャン・ピーターセンがプライベートに週3回行っている隠れた人気企画で、トリップ・アドバイザーの「ボゴタのアクティビティ」では第3位にランクされているほどだ。ウェブサイトで参加日と名前・メールアドレスを登録し、当日集合場所に行けばよく、料金は基本無料で終了時に適当な額を寄付するという、とても気軽な3時間弱のウォーキングツアーだった(筆者は15ドル寄付)。
壁面に現れたビジュアル表現としてのストリート・アートを見るとき、ロゴや単純なキャラクターをスプレーペイントで描くグラフィティ・タイプのものと、多様な技法を使ってより絵画的に表現するミューラル(壁画)タイプのものがあることに気づく。前者はヒップ・ホップ・カルチャーと結びついた若者の自己表現として、後者はアクティビズムやコミュニティ運動と結びついた社会的メッセージ、あるいは都市環境改善の手段として、それぞれ別の発展史をたどってきている。ボゴタでは、両方の流れの影響を受け、ワイルドスタイルのグラフィティから社会問題を戯画化した作品、さらに純粋に楽しさや美を追究する絵画的ミューラルまでが併存・融合しているところに特徴がある。また、「ボゴタは世界一グラフィティに寛容な都市」とクリスチャンが言うように、市民の理解があり、警察も厳しく取り締まることがないことから、時間をかけて丁寧に描き込まれた作品が多い(それでも1作品を1 日か2日で仕上げるそうだが)。個性的なスタイルをもつ人気アーティストが何人(組)もいて、彼らの作品があちこちで見られることからも、ストリート・アートがボゴタの街を彩る重要なエレメントになっていることがわかる。

③グラフィティ・タイプのストリート・アート。MICOのサインが見えるが、地下鉄ペインティングのパイオニアとして知られる彼は、1969年にニューヨークに移住したコロンビア人である。これはMICOがコロンビアに凱旋して、地元のアーティストとコラボレートしたときのもの(“neon”は上から新しく書かれたものでMICOのライティングではない)
今、ボゴタで最も精力的に活動しているアーティストは、Guache(グワッシュ)、DjLu(ディージェー・ルー)、Toxicómano(トキシコマノ=麻薬中毒者)、Lesivo(レシボ=有害な)の4人だろう。ストリートに視覚的かつ政治的・社会的なインパクトを与えることを目的に、それぞれ個人で、あるいはBogota Street Artというコレクティブとして、一目で「あ、これは○○だ」とわかるメッセージ性の強い作品を描き続けている。また、作品集を自費出版したり、ストリート・アートをテーマとしたトークセッションを行うなど、ストリート文化のオピニオン・リーダーの役割も果たしているようだ。写真④から⑦は、彼ら4人が一つの壁で合作した作品である。

④格差社会を風刺しGuacheの作品

⑤“ボゴタのバンクシー”と言われるDjLuのステンシル。彼は、建築家・写真家で、大学で教鞭も執っている。「ストリートを単に移動の経路ではなく、今起こっている何かに気づく場にしたい」という彼の、パイナップル爆弾や機関銃をモチーフにした反戦ピクトグラムは、街の至る所でで発見できる

⑥Toxicomanoはコンシューマリズムや支配階級を批判する作品で知られている。モヒカン頭の「エディ」は、資本主義社会からのはぐれ者キャラクター

⑦資本主義の搾取と富裕層の退廃を風刺するLesivo。右下の王冠をかぶったキャラクターは、ウリベ前大統領のカリカチュアらしい
女性のグラフィティ・アーティストも多数活動しており、最も知られているのがBastardilla(スペイン語で“イタリック”の意)という覆面ミューラリストだ。自身の経験から、レイプ、DV、フェミニズム、貧困などをテーマに、力強い色彩とタッチで描いている。

⑧Bastardillaによる巨大なミューラル
一方、社会的なメッセージ性より、壁画としての表現を追求するタイプのアーティストもいる。Stinkfishは、街で見かけた人物のスナップ写真を用いてその顔を巧みにステンシルしている人気ミューラリスト。個人としての活動のほかに、APCというゆるやかなクルーを結成して、協働製作している場合も多い。Rodez・Nomada・Malegriaの3人は親子で活動しているアーティストだ。イラストレーター、デザイナーとして長いキャリアをもつ父のRodezは、先にグラフィティを始めていた息子のNomadaに勧められてストリート・アートの世界に入ったという。“目”が印象的な彼らの作品はボゴタのストリートでも際立っている。グラフィティ・ツアーのガイドを務めるクリスチャンの作品も市内各所にあった。人物や動物のステンシルをコラージュした壁画のほか、ストリートのアクセサリーとしてさりげなく壁に貼り付けられた小さな陶製のマスクも彼の作品である。
このようにアーティストそれぞれ作風や方向性は異なっていても「ストリート・アートは都市生活への“intervention(介入)”であり、街をを生き生きとさせるもの」という意識は皆に共通し、お互いの作品をレスペクトしているという。

⑨Stinkfishのステンシル。「グラフィティは都市を再生させる手段だ」と彼は言う

⑩Rodezは、息子のNomadaからグラフィティのテクニックを習ったという

⑪Nomada ⑫Malegria

⑬グラフィティ・ツアーの案内人Crispのミューラル。彼はオーストラリアからイギリスを経て3年前にボゴタに移住

⑭右がCrispの陶製マスク。壁からはがしてお土産に持って行く人がいるので、なるべく高いところに貼るのだとか
ボゴタのストリート・アートは、今後、コミッションによる“パブリック・アート”としてのミューラルとゲリラ的なメッセージとしてのグラフィティに、二極化していくかもしれない。
(文/写真:秋葉美知子)