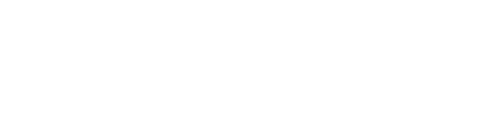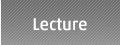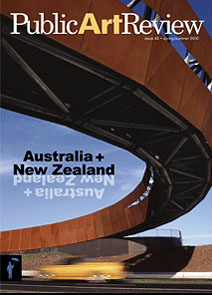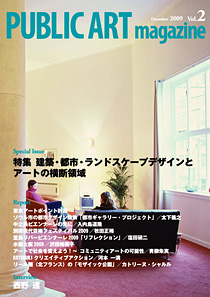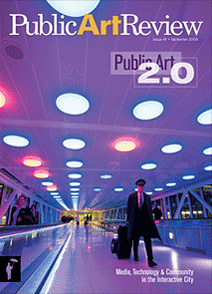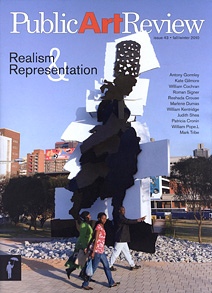
2010年秋冬号<43号> Issue 43 • fall/winter
今号のパブリックアート・レビュー誌は、近年アメリカ合衆国や海外において増加傾向にある具象的表現のパブリックアートを特集している。ゲストエディターに美術評論家パトリシア・フィリップス(Patricia C. Phillips)らを招き、具象的彫刻、人びとの参加を促す作品等を紹介する。さらに、ヨハネスブルグのアパルトヘイト廃止後における自由への開放、ストリートにおけるパブリックアート、メモリアルの考え方に多大な影響を与えた2人のアーティスト等を扱う。
その他に、アメリカの各州におけるパブリックアート・プログラムの連載として、本号ではニューヨーク市でのプログラムを紹介。さらに、アトランタ、セントポール、台湾でのパブリックアートの現状やカリフォルニア州立大学のキャンパスシステムのパブリックアート・プログラム等を取り上げる。
【掲載アーティスト】
Antony Gormley、Kate Gilmore、William Cochran、Roman Signer、Reshada Crouse、Marlene Dumas、William Kentridge、Judith Shea、Patricia Cronin、William Pope.L、Mark Tribe
A4、98頁 オールカラー 定価1,700円