
マディソンスクエア・パーク
マディソンスクエア・パークは、ニューヨーク市マンハッタンのマディソン街とブロードウェイに挟まれた23丁目~26丁目に位置する都市公園だ。その広さは25,000㎡で、およそ東京の日比谷公園の約1/6程度の面積しかない。しかし、歴史的な建築として有名な「フラット・アイアンビル」(1902年竣工)や「エンパイア・ステートビル」(1931年竣工)がすぐ側に見えるという抜群なロケーションにある。スポーツアリーナやコンサート会場で有名な「マディソン・スクエア・ガーデン」とよく勘違いされるが、ミッドタウンの落ち着いたエリアにあり、都会的な雰囲気のある公園だ。ここを管理するのは「マディソンスクエア公園管理局(The Madison Square Park Conservancy)」という非営利管理団体で、ニューヨーク市公園局と連携して、公園内の植栽のメンテナンスや安全管理はもちろんのこと、文化芸術プログラムを実施しているのが特徴だろう。
公園としてのヒストリー
マディソンスクエア・パークは、ニューヨークの中でも活気の溢れる公園の1つだが、今日の姿に至るまでには地元の人びとによる努力の積み重ねがあった。
第4代大統領ジェイムズ・マディソンからその名がつけられ、1847年から都市公園としての長い歴史を持っている。19世紀の終わり頃、この周辺はマンハッタンで最も高級なエリアであったが、1990年代に公園は荒廃していった。ここまではマンハッタンの主要な公園によくある歴史だといえる。実際、数ブロック上にあるもう一つの人気公園の「ブライアント・パーク(Bryant Park)」も同じような憂き目に合い、一時は麻薬と犯罪がはびこる恐ろしい場所に陥ってしまった。マディソンスクエア・パークも、それまでの美しく歴史的な景観は破壊され、うす暗く危険な公園へと変わってしまったのだ。

整備の行き届いた美しい芝生
この問題を解決するため、都市公園財団(マディソンスクエア・パーク管理局の前身)は公園再生のキャンペーンを行なった。その結果、メトロポリタン生命保険、ニューヨーク生命保険などの企業や個人から600万ドルの寄付が集まった。さすが寄付文化が根ざしたアメリカだという声があがるところだが、その後、マディソンスクエア・パーク管理局に変わってからも公園のメンテナンス費用として400万ドルを集めている。
その資金をもとに、公園を19世紀当初の美しいランドスケープに修復し、再びマンハッタンの生活の中心の場となるべく努力を続けた結果、青々とした芝生が再生され、色とりどりの花々や低木などの植栽が戻り、噴水は新たな水循環方式に変わった。さらに新しいエントランスや歩道、街燈も整備されていき、新生したマディソンスクエア・パークは新たな住民を呼び寄せていった。こういった努力の積み重ねにより、再び人びとが行き交う活気を取り戻し、安心して憩える空間に生まれ変わったのだ。

公園内の子供の遊び場
今では、「Shake Shack」という人気のハンバーガー店(New Yorkマガジンで“ベスト・バーガー” (2005年)に選ばれた)に人が集まり、屋外のテラス席ではビールやワインを飲む姿を見ることができる。子供の遊び場はもちろんのこと、愛犬用の「ドッグラン」も整備され、さらに(最近ではめずらしくなくなったが)無料のWi-Fiが整備され、ニューヨーカーに重宝されているようだ。
パブリックアート・プログラム
ゆったりした雰囲気のこの公園には、もう一つユニークな文化プログラムがある。公園に現代アート作品をインスタレーションしていくパブリックアート・プログラムで、マディソンスクエア・パーク管理局がマネジメントしている。このプログラムは、国際的に著名なアーティストやまだ経験の浅い新人アーティストを招聘して、公園にために新たに作品を制作してもらうという、いわゆるコミッション(委託制作)方式が取られている。展示期間は約3か月程度で、パーマネント(恒久的)な展示と異なり、テンポラリー(期間限定的)なプログラムで、世界でも一番といえるほど刺激が多いこの街の人びとを引き付ける工夫がなされている。
このプログラムがはじまった当初、2000-2003年の3年間は、NYの老舗的な非営利芸術団体である「パブリックアート・ファンド(Public Art Fund)」が運営を担っていた。トニー・オースラーやダン·グラハム、マーク・ディオン等の大物アーティストが招聘され、大いに話題を集めた。その後、アートプログラムの担当者を管理局内に置くこととなり、これまでにマーク・ディ・スベロ(2005年)、ソル・ルウィット(2006年)、ロキシー・パイン(2007年)、リチャード・ディーコン(2008年)、川俣正(2008年)、ラファエル・ロサノ=ヘメル(2009年)、アントニー・ゴームリー(2010年)、ジェウメ・プレンサ(2011年)、レオ・ビジャレアル(2013年)等の大物アーティストにコミッションを依頼している。
気になるのはその運営資金だが、ニューヨーク文化部門から公的サポートを受けている他に、多くの民間企業や財団、基金などからの寄付によって成り立っているという、街のなか芸術活動へのサポートが少ない日本と比較すると羨ましい限りだ。
このプログラムに関して、行政側の評価もまずまずで、たとえば、現代のメディチとも言われアート擁護派で有名なブルームバーグNY市長は、「マディソンスクエア·パークは、ニューヨーカーや観光客が好む場所となった。これにはコンテンポラリー・アートプログラムが大いに貢献している。」とご満足の様子だ。
マディソンスクエア・パークのパブリックアート・プログラムの詳細については、「マディソンスクエア・パーク管理局(The Madison Square Park Conservancy)」のHPを参照の事。
Orly Genger’s “Red, Yellow and Blue” (2013) at Madison Square Park
(2013年5月2日〜9月8日まで)

Red, Yellow and Blue (2013), Orly Genger
2013年5月には、オルリー・ジェンガー(Orly Genger)(※1)による『Red, Yellow and Blue』が展示された。作品タイトル通りに赤、黄、青といったカラフルな彫刻的インスタレーション作品だ。公園全体に海の波のようにうねる140万フィート(約426.72km)のロープが創る造形で、マンハッタンのほぼ20倍の長さに及ぶ再利用のロープが使用されたというから驚きだ。3500ガロン(約13,230ℓ)の塗料を使い、完了までには2年以上かかったという。ここでの展示が終わる9月の後は、ボストン郊外にある『
deCordova Sculpture Park Museum』に移設される。

作品のそばで憩うニューヨーカーたち
『Red, Yellow and Blue』は、季節の花々に彩られ緑の木々に覆われたこの公園の中に“上質な介入”をし、公園の景観を鮮やかに変質させている。
解説によると、この作品タイトルである、Red, Yellow,Blueは単に作品の色を表わしているのではなく、「カラーフィールド・ペインティング」でその名を知られるバーネット·ニューマンによる1960年代後半のシリーズ作品『Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue?』からヒントを得ているという。ジェンガ—は、リチャード·セラやフランク·ステラのミニマルリズムの伝統を踏襲しつつ、かつ彼女自身の美学を追求しているようだ。
加えて、作品素材であるロープを“編む”という行為は、どこか親密でドメスティックな女性性を感じさせ、女性の表現の一つであった手芸の伝統を思い起こさせる。しかしその一方で作品のスケール感やモノリシックな表現は“男性的”で揺るぎのない構造を同時につくりだしているといえるだろう。

Red, Yellow and Blue (2013), Orly Genger
(※1)オルリー・ジェンガー Orly Genger(1979〜)
ニューヨーク市ブルックリン在住。2001年ブラウン大学から学士号を取得、2002年シカゴ・アート・インスティテュートで学ぶ。
(文:Yasuyo Kudo)
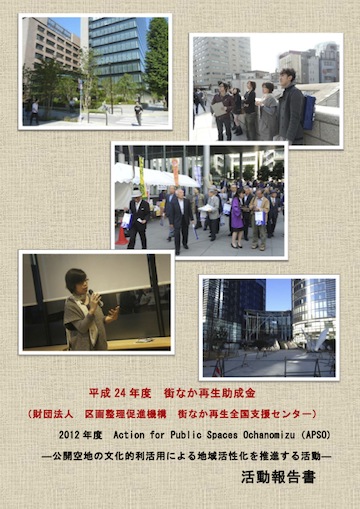
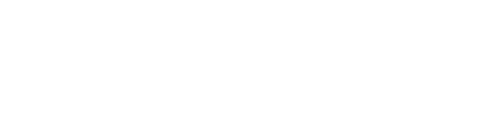




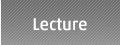
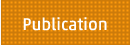




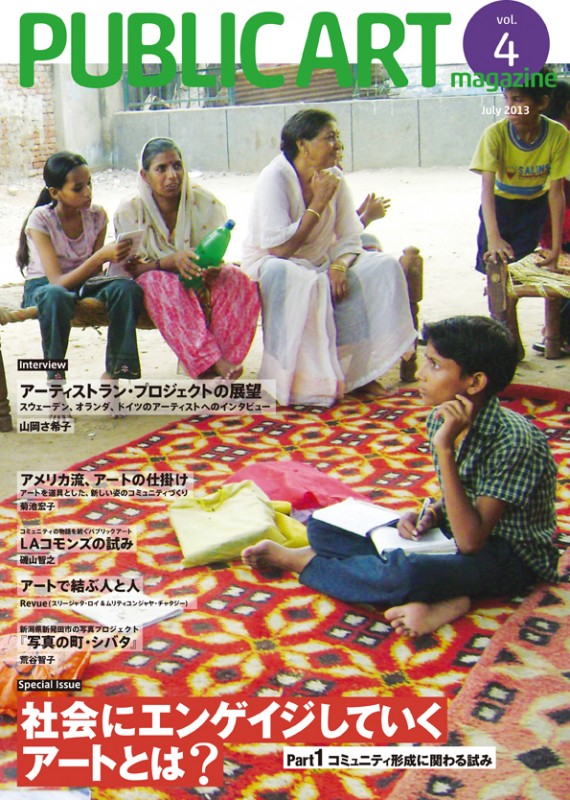






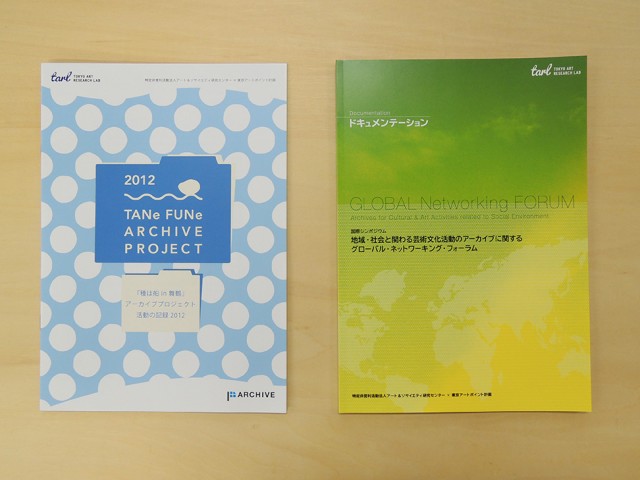







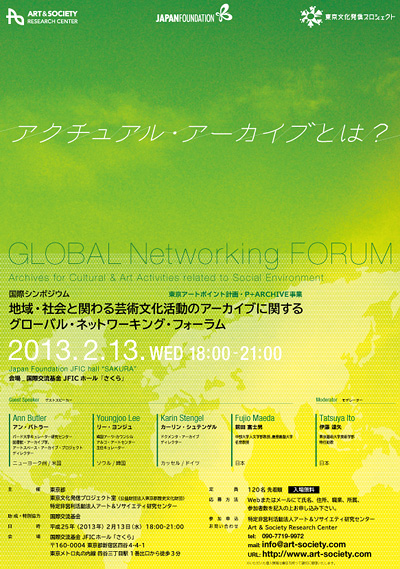

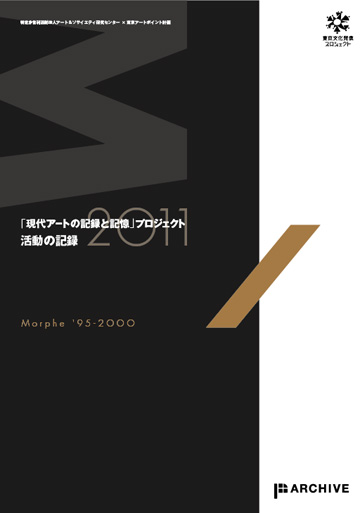
 われわれは今「公的な空間」をどこに求めればよいのでしょうか。アートを通じて国際的にパブリック・スペースの可能性を探ってきた2人のファシリテーターを迎え、パブリック・スペースの多元的な読みとき方に迫ります。
われわれは今「公的な空間」をどこに求めればよいのでしょうか。アートを通じて国際的にパブリック・スペースの可能性を探ってきた2人のファシリテーターを迎え、パブリック・スペースの多元的な読みとき方に迫ります。



