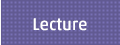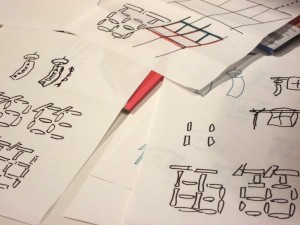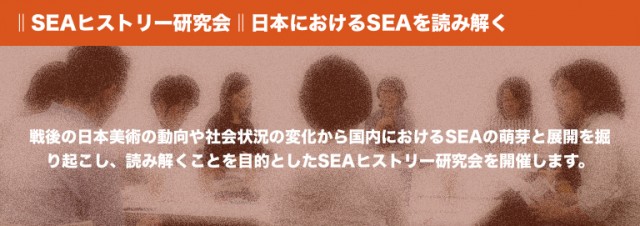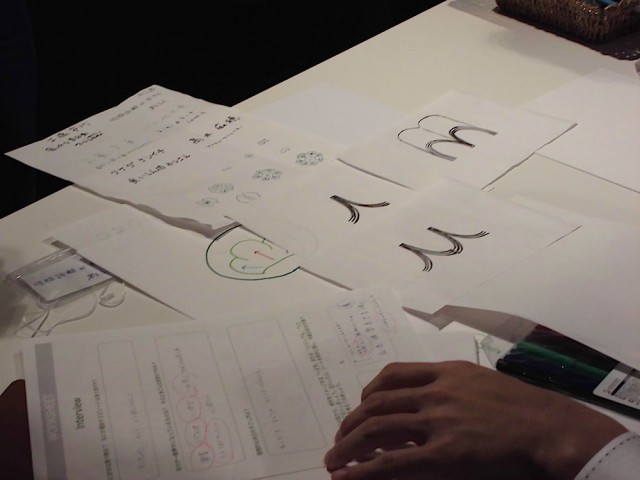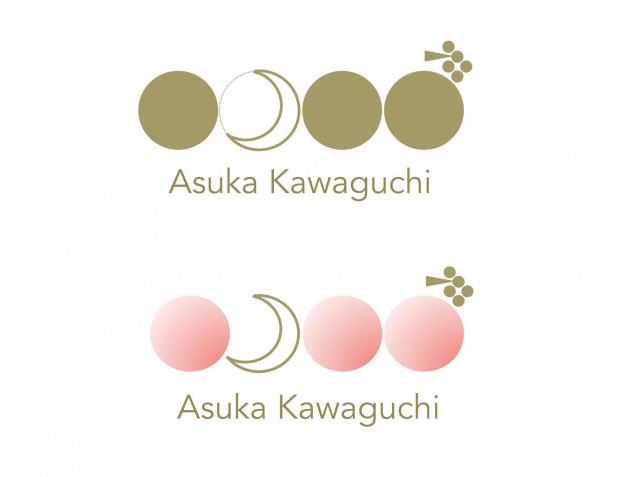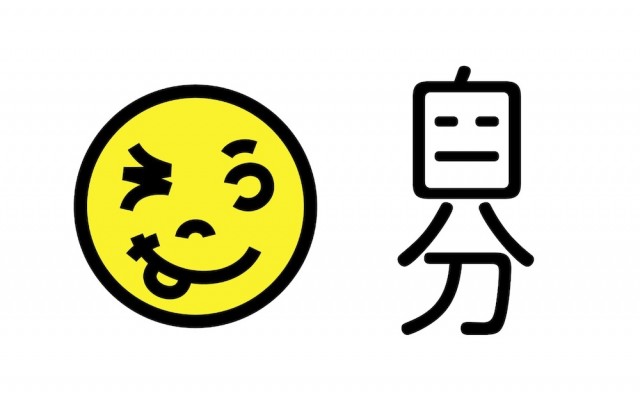La maison centrale de poissy
イカロスとは、父、名工匠ダイダロスの作った蝋で固めた鳥の翼によって空を飛び、迷宮(ラビリンス)からの脱獄に成功したものの、一緒に飛び立った父の忠告を聞かず、太陽に近づきすぎて蝋が溶けて墜死したギリシャ神話の人物です。
昨今の過剰とも思える資本主義と急速なグローバル化変遷の中で、イカロスの問いかける意味、迷宮(ラビリンス)の意味する事はあたかも現在の世界動向を象徴するようで、また、目の前の共同体の中にもそれが存在するがの如くに思えます。
2015年1月、「イカロス」と命名された受刑者とのプロジェクトは、フランス人作家ジュリー・ラマジュ(Julie Ramage)と共に始めました。
彼女はパリ郊外ポワシー刑務所での講師をパリ第7大学人文学社会学リサーチの一環として始めたばかりでした。ジェンダー問題を通し、傷や痕を彷彿させる写真作品を発表していた彼女は、私が行ったパリでの展覧会の出会いから、作家間での共通認識を通して交流していました。
私は、版画における複製品としての役割を消費文化というコンテクストからとらえ、社会と記憶の関わりを考えて活動していました。2014年秋、そんな活動に興味をもったラマジュは私に共同製作を提案してきたのです。
彼女はこの受刑者とのイカロスプロジェクト制作にあたり、アントナン・アルトーの作品を通して、人間や社会における、”傷”、”痕”、”記憶”を問い、またミッシェルフーコーの文献よりライティングワークの概念を提起し、肉体的、精神的、規律と強さ、客観的観察と主観的知覚の混合を通して、社会に問題提示を試みようと投げかけました。そして、この講義を作品として刑務所内と外で発表する事でソーシャリー・エンゲイジド・アートを試みようと考えていました。
留置所の参加者は十数名で各々のテーマをもとにコラージュや、詩、デッサンを提出しました。
私は彼らの作品を銅版画の特製を生かし、厳密にトレースする事で作品のオリジナリティーをフィルタリングし、版に刻まれる“傷”や“痕”、思想を記憶媒体の一つの出来事として複製化出来るのではと提案し、また受刑者本人の作品と特定されない方法で、外部とコミュニケーションする効果を見いだせるのではないかと提案しました。

アトリエでの版画製作過程
このプロジェクトに参加する前提で、自らに問わなければならなかった事の一つに、移民としてフランスに生きる自分の所在でした。そして現実と非現実を横断するシャーマニズムのような“業”的なものを思い描きました。また、日本の裁判による死刑制度とヨーロッパの終身刑制度を通して”近代社会の共同体と倫理観とは?”との視点を思考する機会でなければと思いました。
受刑者達が刑を執行されている保護期間において、更生し再度社会活動を営む為には社会的規範を学ぶ経験と教育が必要とされます。
ただ、昨今のフランスの社会状況を考慮しても受刑者の70%弱(多くがアフリカ、マグレブ系によるイスラム教徒という事です。)が移民出身であり、その問題から来る差別感覚、貧困化、教育の行き届かない現実が犯罪への温床を生み出すとみなされていました。ひいてはフランスのテロ活動を起こしたと言えるイスラム原理主義者は、刑務所内で偏ったコーランの解釈を学び、改宗されていったという報告もなされています。
(まさにこの共同プロジェクトの制作中、アトリエから2ブロック離れた場所でシャルリーエブド襲撃事件は起きました。)
共同作業の中で特に意識した事は、受刑者の身元が特定されない事、そして全ての表現イメージは刑務所の秩序が失われない範囲に限り管理され、刑務所を司る法務局の認可を受ける事でした。一般的に自由であるはずの芸術的表現において、管理下の中で表現を考える緊張感は、とても興味深く貴重な体験でした。
2016年1月、パリ第7大学敷地内にあるベトンサロン(Bétonsalon Centre d’art et de recherché)にてイカロスプロジェクトを発表する機会が訪れました。当日は大学教授そして生徒達を含めて一般の来場もあり、作品を前に多くの意見交換を持てたのではと感じています。
ただこの展示には多方面からの問題提示をしつつも、筆跡心理学(graphology)的見地、災害心理学(désastre)、現在の社会構造や、そこから排除され、再度社会の中へ帰還する法治国家的義務を体現し考察する機会を意図したものだけではありませんでした。
何よりも体験とその経過で生じた物質(substance)を一般社会に投げかけ、そして、そこへの思考過程を共有し、人間と社会の成熟を求める事こそ、社会とアートが切り離せない関係を持っている証とされるのです。

Bétonsalon-centre d’art et de rechercheでの展示会風景
ベトンサロンで発表した作品は、2016年3月、刑務所の中へとステージを変え、展覧会の準備を始める事になります。まずは身分証明書の提出と、留置所へ搬入する全てのリストを事前に提出する事から始まりました。
展示会当日、刑務所敷地内へアクセスするにあたり、8メートルはある高い壁の関係者専用鋼鉄扉が開門され、緊張と好奇心の中で準備を始めました。刑務所の中へアクセスするには、搬入物とそのリストの照らし合わせ、金銭、通信物の厳重なチェック、数回に渡るセキュリティ刑務官の監視の下、錠前の開かれた鉄柵を通過します。私達に準備された場所は、思い描いていた視聴覚室のような一室ではなく、留置所の体育館でありとても広い特殊な環境にありました。
当日、イカロスプロジェクトに参加した受刑者は外部から3人までの身内を招き入れる事が出来、また、この企画に携わった大学側の生徒も十数名参加する事が許可されていましたので、総勢70人弱が参加する事になっていたのです。全ての設置準備を終え、数人の監視員が見守る中、体育館入り口から続々人が現れるのですが、全員が私服姿だったため誰が受刑者なのか最後まで見分けがつきませんでした。
ワークショップが始まるとすぐに、一人の男性が微笑みながら私に近寄り話しかけました。
「君が版画を作った人だね、前々から思い描いていた人で、会いたかった。」
日本人が一人だったため、数人が敬愛の目と珍しさで声をかけてくれました。また、当日はその街のボランティア達が手作りのケーキ、ジュース、コーヒーの差し入れを持ってきてくれ、交流に相応しい和やかな場を提供してくれました。数時間によるこのワークショップでは様々な外部市民、受刑囚、監視員との交流がありました。

版画の原盤を貼付けた鉄の本と トレースした痕の残るカーボン紙の標本オブジェ
特に私にとって印象深かった事は、今でも解読する事が出来ないアラビア風文字で書かれたフランス語の詩を一人の受刑者らしき人から頂いた事でした。
「これは、日本の奈良の大仏を想い書いた物だ。君に渡す為に持って来た。」
数十枚に重ねられたカラフルな A4サイズの紙の中から、一枚を引き抜き私に手渡してくれました。その受刑者は毎日のように詩を書き残すことで、日々満たされているように私には写りました。
このプロジェクトを通して感じた事の一つに、歴史、人、記憶とは伝え、伝わる事で存在し、アートも技術もコミニュ二ケーションをとる事で存在しえるということ。そして、問い続ける事こそ、存在の意義と責任なのではないでしょうか。

受刑者とのコラボレーションによる銅版画作品
(文: 伊藤 英二郎)
Projet conçu et dirigé par Julie Ramage – Avec la collaboration de Eijiro Ito, graveur, Bruno Héloir-Sanchez, artisan métallier, Joffrey Guérin, graphiste, et des étudiants détenus de la Maison centrale de Poissy
Julie Ramage
Eijiro Ito
Bétonsalon-centre d’art et de recherche
伊藤 英二郎 (Eijiro Ito)
1971年岩手県一関市生まれ 。1995年渡仏。版画における複製品としての役割を消費文化というコンテクストからとらえ、社会と記憶の関わりを考えて活動。
現在は写真から得られたイメージを版へ落とし込み、そこへインクを刷り込む版画製作行程によって生み出されるマチエールに近い作品を制作の主としている。