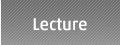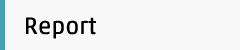10/13-11/10/2002 (作品展示11/9-10)墨田区京島地区
この「アーティスト イン 空き家 2002」プロジェクトは、2000年、慶應義塾大学三宅理一研究室の主導により、墨田区京島地区を活性化を促すアクション・プランとして始められ、今回は2回目となる。地域振興という目標のもと、北欧のアーティストを招き、積極的な住民参加を働きかけた前回に対して、今回はアートが本来持っているはずの可能性を地域と関係づけることを中心課題としたという。この下町の街並みと人間関係がいまでも息づく京島で、ふたりのフランス人アーティストがこの地域に住み、この地域をどのように知覚し、作品化してゆくのか、そしてその作品が地域のひとびとにどのように共有されてゆくのだろうか。
今回の「アーティスト イン 空き家 2002」は、アーティスト・イン・レジデンスを中心に、アーティストと参加者が地域についてともに学ぶ「連続ワークショップ」、学生グループが空き家店舗に住み、開かれたコミュニケーションの場をつくる「京島編集室」、町工場めぐりや学生との商品開発を紹介する「オープン町工場」の4つのプログラムから構成されている。
ここでは、ランドスケープ、都市空間とアートとの関係性についての研究者であるカトリーヌ・グルーをキュレーターとして実施されたアーティスト・イン・レジデンスに焦点をあててリポートする。
関東大震災(1923)や東京大空襲(1945)でも、大きな被害を免れた京島地区は、現在でも小規模な家内工業の工場や木造の住宅や長屋が集積する典型的な木造密集市街地を形成している。このような住環境が防災上の問題をもたらしていると同時に、人口減少、高齢化、地域の産業基盤の落ち込みといった社会問題も抱えている。一方、路地や長屋の前には、敷地からあふれるほどの植木鉢が置かれ、外部空間と家との境界があいまいで、コミュニティで共有化されている。このような環境で、いまでも近所づきあいが密におこなわれ、なにかなつかしい下町の魅力あふれるまちでもある。しかし、このヒューマンスケールな街並みも、現在は古い長屋に空き家や空地が目立ち、それが徐々に駐車場や小規模なマンションへと変貌しつつある。
このような京島にフランスからふたりのアーティスト、カトリーヌ・ボーグランとディディエ・クールボが招かれて、約1ヶ月間住民として生活した。2人のアーティストとも、現代社会や都市空間、個人とその周辺の環境について批判的分析を題材に映像やインスタレーションによる表現を行っている。このアーティスト・イン・レジデンスのテーマは、「家とアクティビティー住むことのリアリティ」。「アーティストはそこに、他者と共に、双方向のコミュニケーションをもって存在しなければならない。」とカトリーヌ・グルーが言うように、ふたりは見知らぬ京島の日常、路地、商店街、町工場などやそこに暮らす人々と日々出会い、ここでしかできない体験をもとに作品の方向性を見出してゆく。実際不思議な体験もしたようだ。利用者はほとんどが高齢者という銭湯に通い、畳のうえでのドローイング。小さな窓辺にはいちじくの植木と自分の名前をいっぱいに書いた窓。このような多様な体験を通じて、アーティストは非常に複層的な作品を生み出すことになった。
カトリーヌ・ボーグランは、12分間のヴィデオ作品「エニグマ(謎)」を制作した。6畳という日本の家の基本的モジュールがヴィデオ・プロジェクションのディメンションと同じという発見により、このヴィデオには常に低層通音のように6畳のラインが浮き出ている。日本の家、自分が京島で住むことになった部屋の畳の線。また同じ画面に、日本の伝統的な木造住宅で使われる柱の木組みのシルエットがやはり淡く重なる。さらには、現在の京島や100年後の東京などについて、親しみやアイロニー、危惧などの感情を込めた6つの質問(謎)が次々と現れ、それについて5つの答えが用意されている。このヴィデオは、実際の空き家の押入に、深海のような、イルカの鳴き声のようなサウンドとともにプロジェクションされた。真っ暗であるはずの押入に光が射す。日常のなかで押し入れられているものが露にされる。京島、空き家、6畳の部屋、押入という空間と、歴史と現実、未来という時間のすべてが複層的に重なり、ジクソーパズルのように一つになる。アーティストが「島のように閉ざされた」と感じた京島への時空を超えたさまざまなメタファーが、いつしか私たちが日々を過ごす現代社会全体へとひろがり、私たちが失いつつあるもの、忘れ去っているもの、または強いて忘れようとしているものを静かに突きつけているようだ。
ディディエ・クールボは、実際に京島のまちかどを敷地として、「何かが起こる」というインスタレーションを2日間展開した。彼は、常にパブリックvs. プライベートという都市の構造に関心を持ち、ヨーロッパの街角の殺風景な場所に、ゲリラ的に花壇をつくったり、ピクニック・テーブルを置いたりして、その場所をヒューマンスケールなものへと突然変貌させることによって、その場所性について問いかけるという行為を行ってきている。そして京島へ住むことになった彼の反応はとてもおかしかった。というのも、彼が今までヨーロッパでおこなってきたことが、ここでは日常的にあふれているというのだ。「ぼくは何もすることがなかった!」彼の関心は、いかにして京島のひとびとが外部空間に少しづつ増殖していくかということとそのワザである。植木鉢のためにひとつひとつ木の台、またはベンチをつくってあげるというような小さなワザのひとつひとつに感心していた。「フランスではこんなことは考えられない。明日になったら植木鉢なんかすぐなくなっているよ。」とも。さらに、彼は、現在の京島が直面する急激な変化にも関心を示し、小規模マンションが建って、道が広げられた場所を自身の敷地として選んだ。その場所には、もはや植木鉢・オン・パレードはみられず、駐車場と道路はコンクリートに固められている。この空間、電信柱の周囲に鮮やかな色のみかんを撒き、道路に水の波紋のようなドローイングを施した。生命感を喚起するオレンジ色は失われつつあるものの存在を露にし、京島に残っているものととそこに起こりつつある変化へと私たちの視線を誘う。そしてちょっと笑えるようなユーモアで、わたしたちが本当に求めるパブリックな空間とはどんなものだろうかと問いかけている。
前回2000年の時、地域振興という目的のもと、銭湯が移動する作品など住民参加をより積極的に打ち出した作品が創られたが、意味がわからない、ちょっと近づきにくいといった感想もあったようだ。住民にとっては初めての経験でもあり、非日常的なものに突然出会ったり参加したりする時の戸惑いが大きかったのかもしれない。(アートへの住民参加やアートによる活性化というと往々にしてこのようなことが起こり得るし、このようなケースが常に否定されるべきではないが。)このような経験をふまえ、今回は周囲から積極的な参加を促すことよりも、日常の自然な双方向の交流から生まれた作品に、日常の風景のなかで出会うことが主眼とされた。結果として、京島のひとびとはいつも住んでいる場所で、自分たちの過去や未来をも含めた時間や空間について静かに問いかける作家やその作品に出会うことになった。そして、日常生活のなかで省みることのない自分たちの「日常性」をあぶり出してくれるような、その存在感に何らかの呼びかけを感じたにちがいない。C.グルーは、「作品が意味をもつには、作品が状況に飲み込まれない力をもち、・・・、人々の姿勢を突き動かすようになる必要がある。」と言っている。アート自体が本来持ちうるこのような可能性が、地域と結びつくとき、それは人々の自発的な参加を生み出してゆく。このような活動を継続して、参加・支援するひとびとの輪を時間をかけて育んでゆくことが、長い目でアートが地域の活性化に貢献できるひとつの可能性を示しているだろう。
(H・S)
このリポートは、2002年11月7日京島で筆者によっておこなわれたカトリーヌ・グルーと2人のアーティスト、カトリーヌ・ボーグラン、ディディエ・クールボへのインタヴューもとにしたものです。
参考資料:同11月18日に東京日仏会館で開催された日仏都市会議2002アートと都市づくり
「クリエイティブが町をよみがえらせる」シンポジウム資料
(慶応義塾大学三宅研究室、東京大学西村・北沢研究室発行)